
Contents
美大に行かないでもデザイナーになれる?
今まで「美大に行かないでデザイナーになる方法」というお題でメルマガ始め色々なところで書かせてもらってきました。「嘘だろ」と言われたり「その通り!」と同意してくれたりと反応は様々ですが別に奇をてらってこんなお題にしてるわけではありません。
どんな人でもやるべきことさえすれば「美大に行かないでデザイナーになれる」とお伝えしたいだけなんですね。
僕自身、美大で学ばせて頂いたので、美大の素晴らしさも良くわかっているつもです。そもそも美大はそれなりの倍率を突破しないと入れないので、美大生はスキルももちろん(デザイナーになるという)覚悟も人一倍強い人ばかりでだと感じています。なのでデザイナーになれる確率はもちろん高いでしょう。
ここで見方を変えて、デザイナーを目指す上で「美大」で学ぶ事で手に入る事やメリットをあげてみてその中から「美大に行かないでも頑張れば手に入る!」ことを抜き出してみたいと思います。その結果、逆説的かもしれませんが「美大に行ないでデザイナーになる方法」が見えて来るはずですはい、では「美大に行かないでも頑張れば手に入る!」ことを見つけるために、まずは「美大で学ぶ」ことで手に入ること・メリットをあげていこうと思います。
美大に行かないでも手に入るもの

まず「美大に行くことのメリット」「美大で学ぶことで手に入ること」を思いつくままあげてみましょう。
- 4年間、学べる時間がある。
- 本当に必要な「デザインの基礎」をいちから学べる
- 有名な教授に学べる
- 沢山のクリエイテイブな作品を浴びるように見ることが出来る
- 幅広い分野を学ぶことが出来る (例えばグラフィックデザイン科であれば、写真や映像等)
- 生涯付き合うことになる友人に出会う確率が高い
- 出来るだけ沢山のデザインを作る事ができる
- 自分の作品集(ポートフォリオ)を作る事が出来る
まだまだありますが、代表的なことはこんな感じでしょうか。
①・③・⑥などは、時間的なことだったり、有名教授の授業、そして友人関係等なので、実際に美大に通わなければ手に入らないことのようです。ここら辺は頑張って時間を作ったり出来るだけお目当ての先生の講演会やワークショップで学ぶ等、やれば出来ると言えますが、美大生に比べ少しむずかしいかもしれません。しかし逆にそれ以外の②・④・⑤は実は美大に行ってない人でも、色々な方法で学べることばかりではないでしょうか?
ではあらためて「美大に通うメリット」の中から「美大に行かないでも頑張れば何とか手に入るもの」を抜き出して並べてみます。
- 本当に必要な「デザインの基礎」をいちから学ぶ
- 沢山のクリエイテイブな作品を浴びるように見る
- 出来るだけ沢山の(全力を尽くした)デザインを作る
- 自分の作品集(ポートフォリオ)を作る
どうでしょう?美大に行かないでもこれらをきちんと実践してみればデザイナーになれる可能性やイメージが膨らんで見えて来ませんか?
種明かしをすればこの4つこそが「美大に行かないでデザイナーになる方法」の「4つの柱」という事です。もちろんこれだけ見ても具体的な方法がわからないかもしれませんのでここからそれぞれ詳細まで具体的にごご説明していきたいと思います。
本当に必要な「デザインの基礎」をいちから学ぶ

デザインに限らず全ての世界で「基礎」は大切です。美大初めきちんとした専門学校では確かに「土台になる部分、つまり基礎・基本」をきちんと教えてくれたりします。そうは言っても「本当に必要なデザインの基礎」というものが、美大や専門学校等に行かないと学ぶことができないような「秘伝の教義?」というわけではなく、情報としてはネットや雑誌等から個人で探せるます。
ただ巷のデザイン参考書等の傾向を見ますと「すぐに使える配色サンプル集!」「ここが間違い?デザインの◯☓クイズ!」みたいな表面的ですぐに使えそうなTips系のものが多いようで、「本当に必要なデザインの基礎」を体系的に論理的に説明し、読んだ人がきちんと理解した上でデザインの現場に活かせるような情報が少ないような気もします。
よく見かける「気軽なテクニック集・サンプル集」というのはすぐに使えますが「どうしてそうなるのか?」という部分の説明は抜けているので読者も理解出来ず、心に残っていない・覚えていないので実際のデザイン制作の現場ではほとんど役に立ちません。ここで取り上げたい・お伝えしたい「本当に必要な基礎」とはそんなものではなく全てのデザイン作業の土台となって一度覚えれば色々な場面で再現・応用出来るようなものです。
もちろん、このページで本当に必要なデザインの基礎を全てお伝えするのは無理ですが、一例として「色」と「レイアウト」について少しだけ書かせてください。
色の3原則(明度)と視認性の関係

「色のど基本」として「色の3大基本原則」というものがあります。「色相・彩度・明度」というもので誰でも一度は聞いたことはあるくらいポピュラーなものでしょう。 色々なデザインの参考書でもここをすっ飛ばしている本は滅多にありません。
少し具体的に説明しますと、視認性とは、そもそもそのデザインで「伝えたい文字情報がユーザーに読めるのか?」という非常に大切な部分です。道路標識で視認性が低いものを作ってしまったら、事故が起きかねないですしセール告知の広告でセールの日にち・期間が見えなかったらどんなに綺麗なデザインだとしても何のために広告出したのか?わからなくなってしまいます。
「視認性」を高める・確保する為に見せたい要素と背景色のの明度差をきちんとつける必要があるのです。つまり視認性を確保するために色の基本原則の「明度」は非常に大切なポイントで「視認性を確保する・高める」為にも「明度」を「色相」「彩度」と分けてまず考えることを、デザインの基礎として教えることこそがいちばん大切なわけです。
本当に必要なデザインの基礎とはこのように、デザイン全体のクオリティを直接関左右したりするので、デザイナーはキチンと筋道立てて覚えしっかりと腹落ちしていなければなりません。逆に言えばそういう風に基礎をひとつひとつ理解出来れば短期間で驚くほどのスキルアップも可能になります。
視認性と明度の関係についてはこちらの記事(視認性について)で詳しく実践的に説明させてもらってます。興味有る方は是非読んでみてください。デザインの基礎がデザイン全体のクオリティをどれだけ左右するものか?少しでも理解頂けたら嬉しいです。
本当に必要な「デザインの基礎」:レイアウト
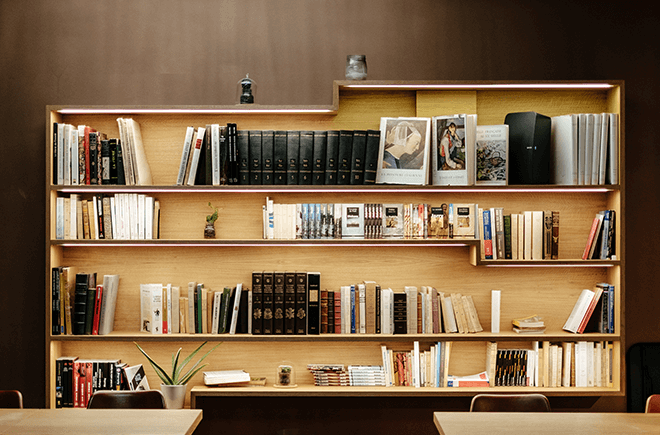
レイアウトも色同様に幾つかの基本法則があります。「レイアウトのの3大基本原則」とはあんまり言いませんが「揃える・集める・崩す」はレイアウトをする上で覚えておいてもらいたいど基本です。 この「揃える・集める・崩す」の法則も例えば数年前に注目を集めたグリッドデザインにおいても活かせる基本法則です。またグリッドデザインに対してのノングリッドデザインというカテゴリーが存在する事も理解しておくとレイアウトについての整理が上手く出来ますし自分のデザインを説明する際の理論武装になるはずです。 他にもFontであったり、デッサン(描写力)等、美大に行かないでデザイナーになるためにはまず「本当に必要なデザインの基礎」をしっかり覚えてください。 デザインを作る場面ではそれぞれの基本を一人で 整理してお伝えしたいので「色」「レイアウト」「フォント」と分けていきますが根がしっかりしている木ほど大きく強く育つものです。
沢山のクリエイテイブな作品を浴びるように見る

もしかすると(一般の人に比べての)「美大生」の一番のアドバンテージは「クオリティの高いデザイン・美術作品」をとにかく沢山見ていることかもしれません。「デザインセンスがあがる」のはもちろんですが(良いものを沢山見ることと同時に)「本当に必要なデザインの基礎」を美大の授業で学んでいるのでそれらが実際にプロのデザインでどのように実践されてるか?の「復習」にもなっているのですね。
「それじゃやっぱり勝てないじゃない」と言われそうですが、別にクオリティの高いデザイン・美術作品が美大の博物館にしか存在しないわけではありませんよね。それどころかあなたの身の回りに溢れるくらいにあるはずです。
まず、ちょっと気分転換に家を出て良いデザインを体感しに行ってみてください。具体的にどのようにしてクオリティの高いデザインを数多く全くお金もかけずに見まくりながら自分の肥やしにしていくのか?下記リンク記事にまとめました!そしてこの方法をより効果的にする為に1で紹介した「本当に必要なデザインの基礎」を学ぶ事と同時進行で進めていくと非常に効果的です。
ライブ的に感じてもらいたいので写真を多く載せさせてもらってます。
出来るだけ沢山のデザインを作る

これはまあ何の世界でも同じかもしれませんが「習うより慣れろ」でとにかく沢山作っていった方が上達が早いですが。また「美大に行かないでデザイナーになる」の「デザイナーになる」という最終のプロセス(作品面接)の時にも雇って貰う会社に作品を見てもらわないと話は進みません。なので未経験だろうと何だろうと作品をストックしておく為にも常に習作を作りつつさておく事が必須になって来ますね。
そしてここでよく聞くのが「仕事をしていないのにどうやって作品を作るのか?」という事です。良い方法が2つあってまずは初心者用に「クオリティの高いデザイン作品を模写する」という方法をオススメします。これは自分のポートフォリオに入れることは流石に出来ないので、本当に「習作」という位置づけになってしまいますが、本気でやるのであればかなり効果的な方法です。
このお話をすると「いやクリエイティブな世界なんだからまずはオリジナルでしょう?」と仰る方もいますが、例えば「唯一無二なオリジナリティ」という言葉が似合うマイケル・ジャクソンがまだジャクソンファイブのグループで兄弟と踊って歌ってた頃、舞台袖で偉大なるJB(ジェイムズ・ブラウン)のステップをひたすらに真似をしていた事を皆さんご存知でしょうか?言われてみると確かにマイケルのステップはジェイムズ・ブラウンの動きに似ているような気がします。(全く踊りの事わかりませんが)
多分マイケルはジェイムズ・ブラウンのステップを真似することでとりあえず「超一流のエンタティナーレベルの動き」までは出来るようになったと言えます。もちろん90%ジェイムズ・ブラウンが作り出し昇華させたステップです。しかし「バイクの二人乗りの後部座席」だろうと何だろうととりあえず同じスピードは体感できたわけです。
デザインでも同じことでとにかく自分が普段作っていないレベルのデザイン作成に参加することであなたの中のクリエイティブなスイッチは押されてしまうのです。
運動科学の世界では出来ない動きを何千回・何万回やっても出来るようにはならないと言います。とにかく人のマネでも何でもいいから一度「自分が出来る動きとして体験」してしまってから何度も繰り返し、自分のデザインレベルをいつの間にか上げていく方法が一番効率的で効果的な方法だと思います。
ある意味、自分さえ騙すようなイメージかもしれません。この方法については下記の記事で詳しく書かせてもらってます。
4.自分の作品集(ポートフォリオ)を作る
これは「3の沢山のデザインを作る」の延長線上にありますが、具体的にデザイナーになろうとする時つまり就職活動をする上でポートフォリオ作成は絶対に必要になりますので、基本的なことだけでもご説明しておきます。
当たり前ですがポートフォリオは誰にでも作れます。抜け・漏れがあったり冊子版であればきれいにプリントされてなかったり普通に見にくかったりするとデザイナーとしてのそもそもの資質を疑われかねませんが、そういう事を気をつけていけば「ポートフォリオ」という作品の装丁・外装(パッケージ)で評価されたりするものではありません。
冊子版であれば一般的なクリアファイル。Web版であれば一覧しやすいレイアウトのWordPressテーマを使えば良いと思います。もちろん例えばWeb版でもろもろscript系にも強いことをアピールするために自分仕様で作り込むことも有効かと思います。(例えば作品のサムネイルをクリック後、ページ遷移せずモーダルウィンドウで大きく見せたりマウスオーバーでサムネイルをさり気なくズーミングしたり等々ですかね)
しかしもしあなたがポートフォリオを作る経験が初めてでしたらまずは冊子版(プリントアウトしてクリアファイルに入れた紙のポートフォリオ)とWeb版の2つをそれぞれ作品数は10個未満で良いので作ってみましょう。プレーンなもので良いです。
次の記事ではプレーンなポートフォリオ作りの方法。
・ポートフォリオに記載する具体的な項目
・メインビジュアルをどのくらいの大きさで見せるか?
・特にWebデザイナーがURL記述する際の注意点
・そして最後にポートフォリオはもちろん、就職活動で意識すると良いマインド等々
実際のサンプルを載せてご紹介してます。転職活動をしようとしている方にも有効です。
ぜひご覧ください。
現役デザイナーが教える転職活動を勝ち抜くためのポートフォリオの作り方
コメントを残す